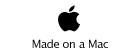KIMURA Architectural Design Lab.
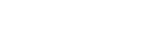
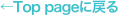


家づくりは、住み手と設計者の苦楽を共にしながらのキャッチボール、
そして、施工者とのコラボレーションの成果です。
木村建築研究室・木村真理子 のHP (女性建築家主宰 建築設計&デザイン事務所 東京都町田市玉川学園)地域の気候風土や文化、その地域らしさ、敷地条件、住まい方等に応じて、自然エネルギーや再生可能エネルギーが最大限に生かされ、身近に手に入る地域の材料をできるだけ使うことで、環境に負担をかけない「呼吸する木の家」「エコハウス」「省エネハウス」を目指した「家づくり・住まいづくり」をしています。断熱・気密・日射遮蔽&導入・蓄熱築冷・通風・換気・調湿・自然素材などの「環境基本性能の確保」と太陽光、太陽熱、風、地中熱、水、バイオマス、敷地の微気候利用、温度差を工夫して生かす「自然・再生可能エネルギーの活用」、そして、エコを意識する暮らしが作り出す「地域のコミュニティの再生」をテーマにしています。 耐震改修・断熱改修や動線等の使い勝手やバリアフリー改修等の住宅改修&リフォームも手がけています。「家づくり相談」にも気軽にお越し下さい。
Policy & Philosophy
家について
■ 暮らしを見直す
家づくりは、暮らしを見直す絶好のチャンスです。 自分と自分の家庭を見直し、自分らしいすまいづくりを目指すこと、その為に考え話し合う過程や葛藤が、その後の暮らしの為にとても大切だと思っています。
家づくりは、そこに暮らすひとりひとりが自分らしくのびのび暮らすための、また将来に渡って安心して暮らすためのうつわづくりです。
■ 家づくりの目指すもの
自分らしい暮らしの実現に向けて、間取りや機能による安全、快適、便利でメンテナンスがラク、目新しいデザインといった尺度だけでは測れない価値や規範(家づくりのプロセスや空間性、職人の仕事の精度、文化風土etc)、又、家族関係や隣人・地域とのかかわり、環境とのつながりについても思いを巡らし設計に反映させています。
出来あがった家が消耗品としてのただの道具ではなく、建主家族の誰にとっても満足・愛着をもって長く大切に使いたくなるよう、そして家族のよりどころとなるように・・。
■ 住み手の立場でつくり手につなぐ
住み手の立場に立ち、どのようにしたら住み手のひとりひとりが日々納得して気持ち良く安心して暮らしていけるかを第一に考えています。そして、建主家族と多くの思いを共有して互いに止揚関係を築き、信頼と協力で課題を克服していく姿勢、住み手にとっての良い家がひいてはまわりにとっても良い家になるようにつくっていく姿勢が大切だと思っています。
また、建主の熱意を引きだし、思いをくみ取り、交通整理をして、確実な技術と発想で施工者の努力と誠意につなげ、かたちとなって実現させること(住み手の要求や期待をつくり手の能力や意欲に確実につなげること)が、設計者の一番の仕事だと思っています。 それが建主の愛着となって住み継がれていき、職人の技術も次代に受け継がれてゆく。。。
消費者vs生産者という形で対峙するのではなく、建主と設計者、施工者の3者が3様に共通の目的に向かって力を合わせていくことが大切だと実感しています。
建主と設計者の良識ある熱意や思いは、全ての循環の源で、個人の住宅はそれが実現できる身近な手段です。
■ 性能バランス、コストバランスを押える。システムや工法は後からついてくるもの
耐震、省エネ、バリアフリー、健康、自然素材etc、住宅性能についての一面的な情報が氾濫し、それらのために様々な工法、システムが開発され宣伝されている昨今ですが、住まいづくりは一面的な性能や商品価値には置き換えられないもっとトータルなもの、地域や暮らしに根ざしたものです。
また、目指す目的(暮らしに望む機能や空間etc)がまず先にあって、システムや工法はそれらを実現するための手段のひとつとして後からついてくるものです。何のための家づくりかということを忘れないことが必要です。
■ 共に生きる視点(環境共生と人間共生)
私たちは、自分達だけ家族だけ、その地域だけ国だけ、さらには人間だけで生きられないことは百も承知です。ですが、先進諸国では、やはり傲慢に暮らしていると思います。 自分達にできることから少しずつ地道に暮らしに反影させていく気持ちが、環境と共生するすまいと暮らしを無理なくつくっていくと思います。
家族の単位が小さくなり、社会の仕組みや家族の意識も個人を単位にと変化しつつあります。しがらみがないことや好きな時に好きなことが気楽にできるのは、確かに楽(らく)ですが、誰も一人では幸せになれません。家族や地域のつながりが薄れて、様々な問題も浮かび上がってきています。
お互いの違いを尊重し認め協力する、「自立して共生する新しい人間関係、家族関係」 を育んでいくことが必要です。今は模索の時期ですが、一部にできつつある 「多様な大家族」 が当たり前のなって来る日も近いのではないでしょうか。
2002.年1月「住まいづくり考」の原稿を書きながら 木村真理子
設計について
家づくりにあたっては、敷地固有の魅力や状況・特徴、自然の恵み、土地柄(風土)、ご家族の状況や好み、廻りとの関系、将来のこと等、それぞれに特別ですから同じ家はふたつとありません。
まずは、ご家族の状況や今の暮らし、今後のこと、趣味や夢や希望などをお聞きしながら、雑談のようにあれこれ話し合うところから始まります。話し合っていくうちに、また話し合いで出た課題を双方が持ち帰り検討していくうちに、自分たちはどのように暮らしたいのか、我が家にとっては何が一番大事なのか等がだんだん整理しされていきます。
家づくりという共通の目的に向かって二人三脚でつくり上げていくのですから、そういう過程をご家族同士また設計者と共有していく過程をおもしろがることも大事です。その上で、図面や模型や参考事例などで確認しながら基本設計をまとめていきす。
基本設計がまとまるころには、新しい家での暮らしがリアルに思い描かれてきていることでしょう。 その後、実物として建ちあげるための細かな仕様の打ち合わせや詳細な設計検討をしながら工事に必要な図面を作成していく実施設計へと進みます。
実施設計がまとまり、予算との擦り合わせや確認手続き等を経て工事会社が決まり工事が始まると、設計意図に違いない丁寧な工事がなされるよう、施工図のチェックや監督・職人との打ち合わせ、現場を確認する設計監理へと進みます。
大切なのは、自分たちらしさを求めるプロセスです。
つまり、住み手と設計者の苦楽を共にしながらのキャッチボールです。
そして、出来上がった家は、住み手と設計者、施工者とのコラボレーションの成果です。
家づくりを楽しみましょう。
Copyright (C)2002−2018 Mariko Kimura, All Rights Reserved.